松本 誠(市民まちづくり研究所、明石市在住)
明石で生まれて、明石公園を「わが家の庭先」とする所に住み始めたのが戦後まもなく3歳のころからだから、他市で暮らした10年ほどを除いて人生の大半を明石公園とともに暮らしてきたことになる。加えて、明石藩士の係累だった曾祖母が明石公園内の二の丸に上がる正面階段下にあった茶店を営んでいたこともあり、父の弟妹はその茶店で出生していることを戸籍から知るなど、明石公園との深い関わりに想いを巡らせていた。
そんな明石公園が、ある日気づいたらお城周辺の樹木が伐採されて、石垣周辺の光景がまるで映画撮影用のオープンセットのように成り果てていたのには驚いた。公園に足を踏み入れたら、まるで「切り株公園」のありさまで、ショックだった。白亜の隅櫓が、豊かに生い茂った緑の樹海に浮かんでいる姿が明石公園を象徴する光景だったからだ。
明石城域は江戸時代から緑豊かな森に包まれていた
この2年ほどの明石公園のあり方をめぐる議論の中で、お城には「戦略上、樹木は少なかった」と樹木と石垣論争で石垣周辺の樹木は「邪魔者」のような議論もあったが、明石公園の歴史を振り返る「明石城史」や「明石公園百年史」など何冊かの記述を見てみると、城内にはうっそうと茂る森のような地域が少なくなかったことがわかる。
考えてみれば、明石城を築城した一帯は人丸山と呼ばれた標高60m程度の上の丸台地であり、明石川と伊川の水利を活かした立地条件にあった。一般的には、城は戦に備えた砦だが、明石城は徳川が全国を平定して「戦のない国」として諸国を抑える要衝として築城されたものだから、御殿も本丸下の平地に造営され、天守閣もない“平時の城”でもあった。廃城令後いち早く公園化された明治以降だけでなく、江戸時代の明石城も緑豊かな自然あふれた城内であったことが幾つもの文献から偲ばれる。
過去には地元市が“公園破壊”の先頭に立ったことも
「過剰伐採」に対して反対運動が立ち上がり、伐採中止を求める運動の中で当時の泉房穂明石市長がしきりに「県立公園から市立公園化」を口にしたことがあった。「姫路も大阪も、全国多くの城跡公園は市立が多いのに、明石はなぜ県立か?」という議論もあった。この議論を聴きながら、私の脳裏に浮かんだのは、歴史と自然豊かな明石公園を都市施設建設の用地としてしか位置付けてこなかった明石市政の過去の歴史だった。
明石城跡が明治以降幾多の変遷を経ながら県立公園として再出発したのは1918年(大正7年4月14日)。翌年1919年(大正8年11月1日)明石市は市制を施行した。戦後は明石市と県などが開催権を取得して、公園内の一画に明石競輪場を1950年に開設。文人知事と言われた阪本勝知事が1961年競輪場を廃止するまで明石公園で公営ギャンブルを続けた。
明石市はまた、1966年には公園東堀を埋め立てて鉄筋4階建て地下1階の市文化会館を建設する計画を県に打診。県の公園管理サイドから難色を示されると、公園西寄りにあったバレーボールコートや東広場、競輪場跡などを次々に候補地に挙げて交渉した。いずれも県は難色を示す中で、史跡や自然を守ろうという市民の反対の声が上がり、県生物学会も反対を表明し立ち往生。1967年の市長選挙で市長が交代し、計画は立ち消えになった。
「公園利活用」の名目のもとに行われたこの時の都市施設建設計画は、当初は当時の市長と知事とのトップ会談では合意されていたが、公園のあり方を守ろうとした公園行政の現場と公園の歴史や自然を守ろうとした市民等の動きが“公園の破壊”を食い止めた。市民の声と文化財や自然保護の運動団体が、ご都合主義の政治にストップをかけた歴史に学ぶことが大いにあると思う。
市民共有の財産を県も市も市民参画の下で守り育てる仕組みを
過剰伐採騒動から、市民と公園行政は公園の維持管理の在り方に、幅広い市民や専門家の意見を反映する仕組みが必要なことを学び、新しい仕組みをつくろうとしている。明石市も「明石公園は県の管理」と突き放した姿勢から、明石のかけがえのない財産であることを再認識し、地元自治体として積極的に関わる姿勢を明らかにした。公園は管理者がどこであれ、公共施設の中では最も市民全体の財産として「コモンズ」性が高いものである。
市民が直接、間接さまざまなチャンネルを通じて、管理や運営に関わることが重要なことを今回の過剰伐採騒動の中でも、あらためて認識できた。市民共有の財産として、市民はもちろん管理者の県も、市民に直接責任を持つ地元の基礎自治体も、それぞれの役割を果たしていくスタート地点に立ったと言える。

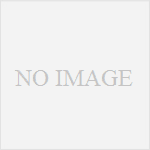
コメント